ENIGMA エニグマ
Hyperion社製 ENIGMA エニグマ の飛行です。スラストベクター付きです。
モーター: Zs2218-14
ESC: ATLAS025LB
バッテリー: LG345-1600-3S
プロペラ: 11x4.7SF
モーターマウント可動部には2.5x6x2.6ベアリングを2個使っています。

動画です。
Hyperion社製 ENIGMA エニグマ の飛行です。スラストベクター付きです。
モーター: Zs2218-14
ESC: ATLAS025LB
バッテリー: LG345-1600-3S
プロペラ: 11x4.7SF
モーターマウント可動部には2.5x6x2.6ベアリングを2個使っています。

動画です。
GWS製F-15が完成しました。これは2機目です。
最初に作ったのは4年前です。この機体は空中分解して大破しました。製作記事と飛行ビデオがあります。よく飛んだので、もう一機購入して保管していました。
今回の機体は、引き込み脚仕様にしました。
機体重量 1090g
静止推力 950g(リポ3セル) 1500g(リポ4セル)
リポはKYPOM製65Cを使用。とてもパワフルです。4セルだと最大80A流れます。
バッテリーを搭載。これからフライトします。

引き込み脚です。引き込み時には前に倒れます。完全には収納できません。

撮影のためローパス飛行中です。

着陸です。

製作記事はこちらにあります。(最初の機体で、固定脚です。)
http://www.wcnet.jp/rc/f15.html
飛行ビデオです。Li-Po 3セル(KYPOM 65C)でフライトしました。引き込み脚が不調だったので、脚は出したままです)
飛行ビデオです。4年前に製作した機体です。Li-Po 4セル(Hyperion 25C)でフライトしました。
引き込み脚の動作の様子です。
![]()
NFD-S288 ICON A5が届きました。
実機にならって水陸両用設計になっています。
以下、このラジコンの話です。
ICON A5 Amphibious airplane(EPO)
Product NO.: S288 ICON A5-10class
Length:720mm.
Wing span:1090mm.
Wing Area:16.3dm2
Wing load:28g/dm2
Radio:4ch,4 servo
Motor:A2208 kv1000
Propeller:APC 7*4 or 6*4E
Bettery:11.1V 1000-1300mAh
Flying weight:490g(on ground),470g(on water).
Flying time: 15minutes
脚は取り外しできるようになっています。 水中舵と前輪はラダーに連動します。 フラップは付いていますが、サーボ取り付け枠がありません。
購入したものは機体のみで7,470円でした。 プラス5,040円で、サーボx4、ESC、モーターが付属します。
キットの中身
![]()
素材はEPO(発泡スチロール)ですが、少し硬めで、光沢があります。
主翼に取り付けるサーボは厚さ12mmまでOKのようです。 JR DS-385(NES-371)が、ぴったりフィットしました。
組み立て説明書は、全10ページにわたるオールカラーの立派なものです。
実際は、ほとんど工場組み立て済みです。
デカール貼り、主翼にフックを接着、水平尾翼を接着、左右のフロートを接着、リンケージ、モーターマウントの接着、モーター・ESC・サーボ・受信機・バッテリーのインストール、で完成です。
デカールが変更になったみたいです。 赤部分が多く、派手になりました。
デカールにシミがありました。 プリンターの不具合でしょう。 あきらめるか。
![]() NFD-S288 ICON A5組み立て説明書のダウンロード
NFD-S288 ICON A5組み立て説明書のダウンロード
![]()
![]()
![]()
今が水上機のシーズンなので、急いで組み立て作業にかかりたいと思います。
|
エルロン用サーボのリード線は600mmに延長しました。 |
付属のロッドとホーンとは相性が悪く、ガタガタでしたので、自作しました。テトラ製アジャストチップMB型を使いました。 長さ約50mm。 重量=1g。 |
|
|
主翼前側に接着するコネクトピース(ベニヤ板)ですが、胴体側の幅に合わせます。 (矯正します) |
エレベータ用のリンケージロッド先端はZベンドされていますが、曲げが鈍角すぎたので、再度Zベンダで修正しました。 |
|
|
エレベーター用のリンケージロッドは、一旦引き抜き、グリースを塗布します。ラダーも同様。 |
水平尾翼の接着はエポキシ接着剤を使用しました。 垂直尾翼とはめ込みになっていますが、ピタリ合わせると水平になりませんでした。注意! ! |
|
|
ラダー用サーボホーンに取り付けるロッカーアームの穴径を1.8mmにします。 リンケージロッドが2本入ります。 |
モータマウントです。 モーターのリード線が通りやすいように削りました。 |
|
|
使用したESCです。 モーター用コネクタは2mmです。 |
使用したモーターです。脱着の都合で、リード線を150mm延長しました。ケーブルは18AWGです。 |
|
|
バッテリーホルダーです。3mm厚バルサ材を貼りました。前輪ステアリング用のリンケージロッドが通るためです。この上にスポンジテープを貼り、両面ベロクロステープでバッテリーを固定します。 |
胴体底部にはワンウェイ ドレイン バルブが付いています。 ふさがないように注意!! |
|
|
プロペラの取り付けに注意!! モーターは後ろ向きですが、プロペラの前面(刻印がある側)を前にします。 つまり、プロペラの前面からモーターに差し込みます。 逆向きだと推力が半減します。 |
|
![]()
苦戦しました。修正が必要です。
まず、浸水が激しかった。短時間で、かなりの量の水が入っていた。
⇒ その場で、ビニールテープでシールしました。
スピードに乗らない。
写真でわかるように、少し速度が上がるとサイドのフロートで発生した波がプロペラに直撃!水しぶきをあげて、スローダウン。・・・この繰り返し・・・
あきらめて、ボートとして楽しんでいた。
ハーフパワーで円を描くように旋回していました。少しでもプレーニングしやすいようにとエレベーターをフルアップでタキシングしていました。
そのとき、
半分プレーニング状態になったので、これは、、と思いフルパワーにしたら
プレーニング状態に入り、離水した。
しかし、
これは、コントロールできない!! 水面にポチャ!! 10秒程度のフライト時間でした。
機体は無事でした。
次の点を再調整して、次回トライします。
・ 機体の軽量化。バッテリーを小さいものにするしかありません。 1300mAh → 800mAh
・ 重心位置の見直し。
・ 防水処理。
![]()
この機体については、次の点の変更・調整をもって終結します。
・ 重心位置の調整
・ 水平尾翼の取付角度の調整
・ 水上機専用とした
・ 防水処理
・ 接着のやり直し
◆ 重心位置の調整
当初、かなりUP側にトリム調整していたので、重心位置を後へ移動させて飛行テストをおこないました。 すると、操縦不能(翼端失速か?)、クリクリ墜落、飛行テストを繰り返した結果
組立説明書どおりの33mmが適当だったことがわかりました。
主翼が前進翼です。重心位置は胴体に最も近いところの主翼前縁から33mmです。
メカの配置を変更しました。
![]()
◆ 水平尾翼の取付角度の調整
真横からよく見ると、水平尾翼の前が上に向いていました(?)。 段差が付いていました。
水平尾翼は垂直尾翼にはめ込むようになっていて、はめ込んだ状態で前後左右には動きません。
トリムUPの改善にもつながると思い、
水平尾翼を取り外し、垂直尾翼上部を少し削り、前側の段差が無くなるように調整しました。
![]()
◆ 水上機専用とした
前車輪の付け根から浸水するので、前車輪の部品を全て取り去り、バスコークで埋めました。
不要になったパーツ
![]()
◆ 防水処理
ほとんど工場組み立て済みなのですが、接着部から浸水しました。 接着部をナイフで広げるようにしながら、ボンドを詰め込みました。
特に、機首部分から水が入りやすいので、防水を強化する必要があります。
![]()
また、ベニヤ板に防水処理を施しました。 適当な塗料が無かったので、エポキシ接着剤を薄く塗布しました。
◆ 接着のやり直し
水平尾翼を取り外す際に気が付きました。
エポキシ接着剤で接着しているにもかかわらず、少しの力できれいに剥離しました。付着している接着剤もフィルム状態で剥離しました。
サイドフロートも同様でした。
そこで、サンドペーパー#100で接着面を荒らし、接着し直しました。
◆ フライトの感想
(離水)
少し速度が上がるとサイドのフロートで発生した波がプロペラに直撃!水しぶきをあげて、スローダウン。・・・この繰り返し・・・
⇒ 機体を水平に保ち、徐々に加速する。 といっても、難しいです。 機体が傾く方向と逆方向にラダー(水中舵)をあて、旋回させながら加速していく。 フロート底部がV字型になっているので、ラダーをあてた方向に傾きます。 プレーニング状態に入ればエルロンも効きますが、それまでが苦労します。
(上空飛行)
飛行性能は、良いとはいえません。
直進性が悪く、ロール軸方向に不安定。 多少浮きにくい。
ロール、ループ、背面での8の字旋回飛行、全てできましたが、良いとはいえません。特にロールは、修正舵を入れるほど、ひどくあばれます。一定の速度で回転せず、「ひっくり返る」感じになります。
⇒ スケール感を楽しむ機体です。
(着水)
跳ねます。
⇒ 跳ねやすいことは事実ですが、操縦技術を向上させる。
私が属しているクラブの飛行場です。
最近アクティビティが下がり、なかなか人が集まりません。これでも多い方なんですよ。

写真手前がNS氏のSUKHOI 29S 140E、スパン1940mm、機体総重量4600g、なんと静止推力は10kg以上あるんです。
写真奥はMY氏のT-REX600E FBLベースのジェットレンジャーです。

・SUKHOI 29S 140Eの飛行ビデオ
・T-REX600E FBLベースのジェットレンジャーの飛行ビデオ
・MU氏によるHIROBO製スカディ50の飛行ビデオ
私が属しているクラブの飛行場です。
動画はiPadで撮影しました。ズーム機能が無いため機体が小さくて見ずらいと思います。
YouTubeの全画面表示でご覧ください。

◆ TK氏のT-REX700Nitro

◆ YS氏のプライマス50 北西モデル製

◆ MY氏のシーガル カシオペア製
水陸両用なんです。

(ただいま更新中)
MY氏によるカシオペア製シーガルの飛行です。
私は、ICON A5を飛ばしました。
RC/Gクラフトで購入した「機体発見ブザー TypeⅠ」です。
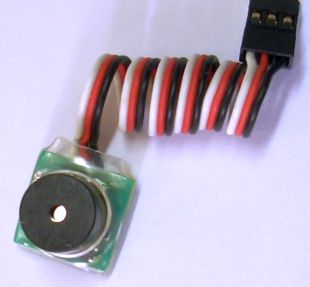
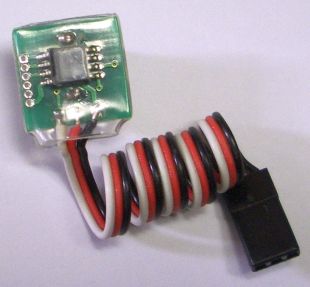
RC/Gクラフト
http://www.rc-gcraft.com/index.html
空きチャンネルに接続するタイプで、580円でした。 小型・軽量で音量も大きく、良かったです。
電源投入時に、確認の「ピー」となります。 アラーム音は「ピー・ピッ・ピッ・ピッ・ピッ・ピッ・ピー」の繰り返しです。
連続音より聞き取りやすいと思います。
信号のパルス幅が1750μ秒を超えると鳴ります。 ニュートラル(1500μ秒)付近に設定していない点も気に入りました。
コネクターはJRタイプですので、FUTABAもOKです。
JR受信機に装着すると、少しきつめなので、コネクタハウジングを少し削るとよいでしょう。
(実測値)
大きさ: 16mm(W) x 16mm(D) x 13.5mm(H) (基板のみ、凸部を含む)
重量: 4.7g (ケーブルを含む)
ケーブル長: 190mm (基板からコネクタ手前まで)
ON/OFFのしきい値: 1750μsec
待機電流: 20mA
最大電流: 250mA (ブザー稼働時、断続音なので平均値は150mA程度です)
ATMEL製AVR8ビットマイコン「Tiny13/A」を使っています。 ブザーはHYDS(中国製)です。
StevS 30E によるアクロフライトです。
パイロットは、N氏です。
このような入門機でもアクロフライトが可能です。 ジャイロ等は搭載しておりません。
ご覧ください。
2013.1.08 レンダリングをやり直しました。
Nさんへ
この飛行機の詳細を教えてください。
モーター、バッテリー、ESC、プロペラ、など。
RC Factry製 Crack Yak Gold BACKYARD です。 素材は、壊れにくいEPPです。

ただ今、組み立て途中です。
サーボ(HITEC HS-55x3)とリンケージが完了しました。
現在までの、重量は、107g です。 バッテリーを含む飛行重量は、250g位になりそうです。
RC Factry
RC Factry製 Crack Yak Gold BACKYARD
組立説明書のダウンロードや組立解説ビデオが見られます。
RC Factry製 Crack YAK 55 が完成しました。
【私の仕様】
機 体: RC Factry Crack YAK 55 ( EPP素材、全幅800mm、全長830mm )
ランディング ギア: RC Factry 0,80m SP01
モーター: T-MOTOR AT2206-17 1500KV
プロペラ: APC 9x4.7SF
ESC: DUALSKY XC1010BA 10Amax
サーボ: HITEC HS-55 3個
ジャイロ: DUALSKY FC130
受信機: JRプロポ RD631
送信機: JRプロポ DSX9
バッテリー: ROBIN 7.4V 600mAh 20C (33g)
飛行重量: 223g (機体190g + バッテリー33g)



受信機とジャイロは、0.3mm厚のプラ板をScotchプラスチック用ボンドで機体に貼り付け、その上から両面テープで貼り付けました。
これは、再利用を考えた結果です。
ケーブルの結束に用いたものは、100円ショップで購入した「のび~るテグス」です。
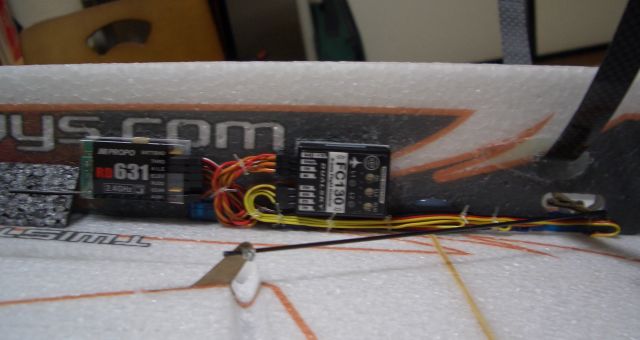
ESCは、ホットボンドで接着しました。
バッテリーは、糊付ベロクロテープで固定、機体側は、剥がれないように、瞬間接着剤を併用しました。
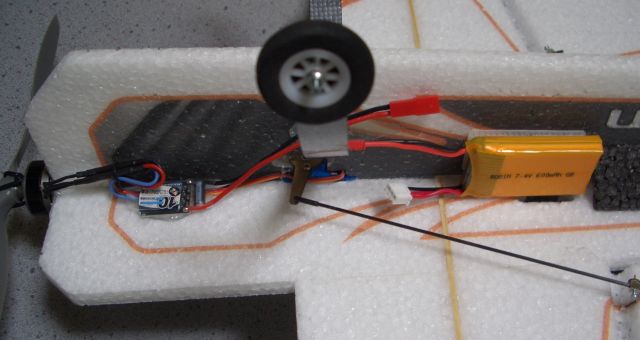
EPPの接着に用いた「Scotchプラスチック用ボンド」です。

ランディングギアセットのスパッツを組み立てましたが、タイヤハウスが狭くて、そのままでは利用できません。

スパッツを加工するのも面倒なので、使用するのを断念しました。


DUALSKYのESCには2.5mmのメスコネクターが付いていましたが、オス側が無かったので、
ESC、モーター共に、2mmコネクターに交換しました。

DUALSKYのFC130ジャイロ本体(8g)に付属していたケーブルの重量が、本体より重かったので(笑)
他のケーブルを加工して使用しました。

ラダーの底面に0.5mm厚プラ板を貼りました。
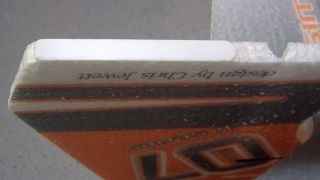
・ バッテリーを除いた状態で、重心位置が組立説明書どおり(モーターマウントから後ろへ210mm)になりました。
これで、バッテリーを重心位置に搭載でき、バッテリー重量が変わってもOKです。
・ 静止推力は約380gfでした。
・ プロポやジャイロの設定は終了しました。 後はテスト飛行で調整するのみです。
DUALSKYのFC130ジャイロは、初めて使用しました。
このジャイロの設定方法を記事にしたいと考えています。
2013/11/16 ビデオを更新しました。 訂正と補足があります。
DUALSKY FC130ジャイロは、初めて使いました。
安価で、軽量でしたので、前記事のEPP機に用いました。
設定方法をビデオにまとめてみました。
機体を静止させた状態で、ヘディングロックモードに切り替えると、全ての舵がゆっくり動きます。
この現象は、ドリフトと言うより、不感帯が無い、と言った方が適切かもしれません。
そもそもヘディングロックモードにはニュートラルは無いので、実際の飛行には問題ありません。
(注意)
・ 設定後の動作チェックは、ジャイロの電源を再投入してから行ってください。
・ ジャイロをOFFからノーマルモードに切り替えた時、各舵のニュートラルが微妙に変化する場合や、
ヘディングロックモード時のドリフトが多い場合は、
FC130ジャイロのキャリブレーション(ニュートラルのみでOK)を再度行ってみてください。
FC130の取扱説明書(日本語)のダウンロード
http://www.flyingcattokyo.sakura.ne.jp/zz_ProductInfo/DualSky/DualSky-FC130-JP-Inst.pdf
実際に飛行させて、また記事にします。
RC Factory Crack YAK55 に DUALSKY FC130ジャイロを搭載して、
楽々トルクロール・・・
FC130ジャイロは、安価(4,000円弱)で、軽量(8g)です。
使用してみて、操作フィーリングも良好でした。
感度調整VRの位置は、
エルロン ・・・ 最低
エレベーター ・・・ 中央
ラダー ・・・ 中央
使用したサーボは、各舵とも、HITEC HS-55 (アナログ、1.1kgcm、0.17sec/60°)です。
このサーボは、保持トルクが弱く、スピードも速くありませんが、ニュートラル性は良好です。
以前、安価(1,000円未満)なサーボを何種類か使ってみましたが、ニュートラル性が悪くて、
ゴミになっているサーボが多数あります(笑)
OS製60ccガソリンエンジンを搭載しています。
私のHP「Sunday Flyer」で、重心位置を求めることができます。
長期に渡り更新されていませんが・・・ごめんなさい。
TOPページ
http://www.wcnet.jp/rc/
重心を求めるページ
http://www.wcnet.jp/rc/cg_calc.html
ソースコードを公開します。
PHPでプログラムしております。 お粗末なプログラムですが、ご自由にご利用ください。
注)私のWebサーバーでは、拡張子.htmlでもPHPが実行されるように設定しております。
F-16(ファイティングファルコン) 90mmEDF機が届きました。
近年のEDF機は、昔と比べ、とてもパワフルで、フィン(ペラ)の枚数の多いものはジェット機に似た音色がします。
購入しました!!>> F-16
私は、数あるジェット戦闘機の中で、このF-16のスタイルが一番好きです。
キット(ARF)の内容物です。 2段の重箱に梱包されています。
上の段には、翼の部品が、下の段には胴体が収納されています。

胴体下部には、吸気口が設けられています。
実際の吸気口だけだと、 排気口>吸気口 となり、パワーダウンしますので。

ドア付の引込脚です。引込脚のパーツは全て実装済みのようです。

各種サーボ・リンケージも実装済みです。

ミサイルなどの装飾部品も、全て塗装済みです。
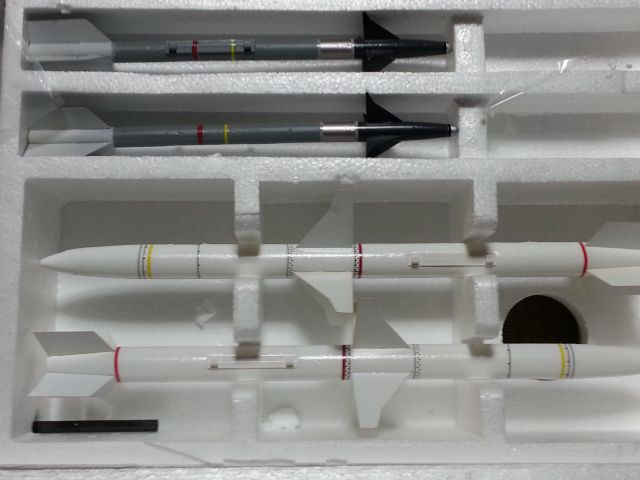
組立説明書ですが、ほとんどが工場にて組み立て済みです。
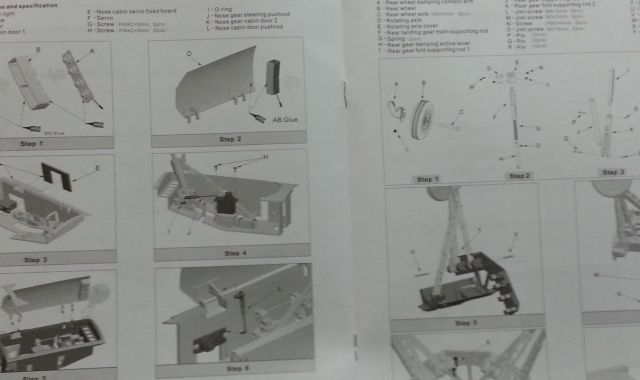
アップグレードバージョンがあるようです。
スタンダードバージョンとの違いは、モーターがインライナーになって、推力が250gほどアップしています。
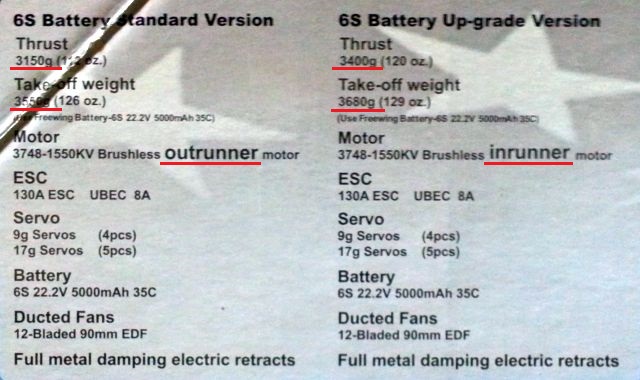
組立は、
胴体に翼を接着し、ESC、サーボミキサーなどとRC装置との連携作業のみのようです。
(主翼は脱着可能です)
進捗状況を、順次、掲載していく予定です。
それと、CL-84ダイナヴァートを注文しちゃいました。
これは、オスプレイの原型ともいえる機体です。
こんな、感じで飛ぶようです。
http://youtu.be/ChVYq6ggVRw
実物が手元に届き、自分の手で操縦してから、また、感想や動画をアップしたいと思います。
FreeWing製F-16が、ほぼ完成しました。
エレベーターサーボ(左右2個)をHyperion製DS13-ACBと交換しました。
純正サーボが、不具合だったためです。
Hyperion製デジタルサーボは、プログラムによりリバース設定が可能です。



あと2時間ほどで、新年を迎えます。
2015年も良い年になりますように・・・
Unique model 社製 CL-84 を初フライトしました。
Battery: 4S 2200mAh 65C
TX: HITEC AURORA9X
RX: HITEC OPTIMA 6 Light


初飛行の様子 take1
初飛行の様子 take2
初飛行の様子 take3
ヘリモードにて、ホバーリングするように、トリム調整しました。
その結果、エレベーターUP側にっぱいにトリムが移動しました。 飛行機モードに切り替えてみると、すごくUP側になっています。
これでは、・・・ と思い、ミキシングで、飛行機モード時にエレベーターが水平になるようにしました。
とりあえず、いってみるか!? (take1)
ヘリモードから飛行機モードに移行、エレベーターはUP側のままでないと機体が降下します。
旋回時に、エルロンを中立にすると機体が水平に戻ります。・・・これって、ジャイロが常に働いている!
それと、エレベーターの操作量が少なすぎて、大回りの旋回しかできない。
無意識に、ラダーを操作していました。 この機体は、飛行機モードのときラダーは無効なのです。
ミキシング量を1/3に take2
take1で、飛行機モード時に、UPトリムが必要と分かったので、エレベーターにUPトリムを入れました。
風の影響を大きく受ける take3
ヘリモード時には、主翼に風が当たるので、しかたありません。
今日は、吹き流しが真横になるくらいの風でしたが、CL-84を飛行させました。
このビデオの後、離陸させましたが、強風が長く続いたため、機体が後進しながらの強行着陸となりました。
主翼端とエレベーターに少し傷がついた程度ですみ、ラッキーでした。
ビデオ撮影して下さった、KROKさん、ならびにMIURさん、ありがとうございました。
MyuさんのUコン機です。
う~ん、簡単なようで、難しい・・・

CL-84は、ほとんどが工場にて組み立て済みなので、組立時間は、ほんのわずかです。
組立中に、気づいた点をノートしておきます。
●リトラクタとセンサーです。 このセンサーでヘリモードか飛行機モードか検知しています。

●コネクターの半田付けが・・・
少量の半田で付けられています。電気的にはOKですが、機械的には弱いので、気になるようでしたら、やり直した方が良いかも・・・
私は、Tコネクターに取り換えました。

●水平尾翼の取付
ネジがベニヤ板に食い込みそうでしたので、平ワッシャ―を入れました。

●メインギアの取付
ピアノ線をはめ込む部分の溝(凹部分)を修正しました。

●バッテリーホルダーの自作
バッテリー位置にセメダイン製「防水すきま用テープ」を、バッテリー固定には、ベルクロテープ(粘着剤無)を使用しました。
ベルクロテープの固定は、胴体にナイフで切り込みを入れエポキシ接着剤で固定しました。
抜ける心配はありません。

●ノーズギア
説明書には、「フリーにしておきます。」と書かれていましたが、実際の飛行では、前後に移動できた方が良いと分かったので、
ゴムブッシングを入れました。完全固定ではないので、手で回せますが、飛行中の振動では回りません。

●主翼ハッチを取り付けたら・・・主翼をリトラクトしたとき「バキッバキッ」と異音がするようになった
ハッチのベニヤ板(写真の赤部分)を削りました。

●ラダーサーボが破損しました。
何度目かの着地の際、テールが地面に接触したときです。そのとき、破損(ギヤ欠け)したみたいです。
Hyperion製DS-11AMB(デジタル、メタルギヤ)と交換しました。サイズは、ほぼ同じです。


CL-84の前車輪をラダー操作できるようにしました。

プロペラのダイヤが大きく、プロペラ先端と地面との距離は、わずか4cmです。
滑走による離着陸は難しそうです。
とりあえず、タキシングができれば恰好良いかな!? と考えています。
ヘリモードに移行した瞬間・・・
テールモーターが離脱し、墜落しました!!
そのときの動画です。
最後まで、あきらめなかった成果か!?
リペア可能です。
このモデルの欠陥かな!? 改善しなければ・・・

私では、ありませんが・・・
YouTubeで、偶然見つけました。
ガスボンベ(ライター用かな?)を搭載、点火にはスタンガンを改造して使っています。
音がすばらしい!! まるでジェットエンジン
やってみたい、とも思いますが、火事になったら大変!!
垂直離着陸機CL-84の修理が完了して、約1ヵ月たちました。
テストを兼ねてフライトしました。
ノーズギアはラダーと連動して、タキシングができます。
離陸から着陸までを撮影しました。
次は、飛行機モード時にラダーが効くように改造しようと考えています。
Flight Model製 mini Excellence です。
クラブ仲間が飛ばしているのを見て、気に入りました。

バルサリブ組フイルム張り半完成機です。
電動とエンジンの両方の仕様に対応しており、モーターマウント、エンジンマウント、燃料タンクなどが
付属します。
バルクヘッドも、ウレタン塗装済みです。 フィルムはオラカバで、丈夫です。
樹脂製のスピンナーが付属していますが、バランスの悪化を考え、使用していません。
この機体は、フロントヘビーになりやすいです。
そのため、できるだけ前を軽く、後ろを重くすることを心掛けてメカ搭載などを行いました。
翼長: 1020mm
全長: 980mm
翼面積:20.5dm2
飛行重量は、11.1V 2200mAh Li-Po搭載時で、 950gです。
モーター: Hyperion Zs2218-14
ESC: HobbyWing FLYFUN 30A
バッテリー: Kypom 3S1P 11.1V 2200mAh 65C
プロペラ: APC 11x4.7SF
バルクヘッドへのモーターマウントの取り付けはボルトナットでしたが、機首部の軽量化を考え、
エポキシ接着剤で接着しました。
モーターはHyperion Zs2218-14 (960KV)で、現在では製造終了品です。
ESCはHobbyWing FLYFUN 30A(Li-Po2~4セル対応)です。
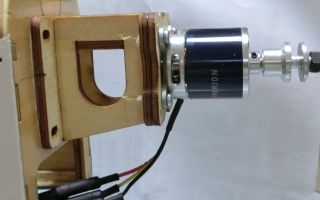

受信機はHITEC OPTIMA6です。 OPTIMA6はテレメトリー対応、SPC有、DATA無で、
動力用バッテリー電圧のみ送信機側でモニターできます。
ジャイロはDualsky FC130 V2 で、フラッペロン対応ですが、フラップは使用していません。
左右のエルロンサーボは並列接続しています。
受信機搭載用にベニヤ板でベットを自作しました。
メンテナンスを考慮し、タッピングビス4本で固定しています。
図面は、この記事の最後にあります。

メインギアは、ENIGMAエニグマのものを使いました。 純正品はアルミ製です。
純正品と比べ、少々のj軽量化と、機体高が10mm程度高くなります。
尾輪もエニグマのものを使いました。
純正品と比べ、少々重くなりますが、車輪径が大きく転がりやすいです。


エルロンx2、エレベーター、ラダー全てのサーボはHyperion DS09-SCD です。
リンケージロッドとラダーホーンはエニグマのものを使いました。
純正品は金属製アジャスターロッドと2カ所ネジ止めのホーンです。
固定長のカーボンロッドですが、あらかじめホーンの直角を出しておき、後で、ニュートラル、
最大舵角、方向をサーボプログラマーを使って設定します。



次の表は、私が実際に測定した機体静止時の値です。
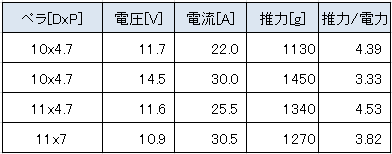
(注意)
ヒンジは、別途テトラ製のものを購入しました。 純正品は、接着面が剥離しやすく、
信頼性がイマイチ・・・と思って、使わないことにしました。
実寸大ですので、印刷し、板に貼り付け、加工するとピッタシ合うと思います。
10月2日(日)12:00~
久しぶりに飛行場に行きました。I氏とM氏、私を含めて3名です。
それから、2時間ほど経過したころ、3名の方が来られました。
我クラブもアクティビティが下がりました。

写真はYAK55でトルクロールしている時、M氏に撮影してもらいました。
関連ページ
http://www.wcnet.jp/lily/blog0/2013/11/crack_yak_55_1.html
最近、ラジコン航空機を、まったく製作・飛行させていないので、新しい話題がありません。
ちょと、昔を振り返ってみます。
2008年に製作したA-380です。機体は発砲スチロールでできています。
芝生の滑走路を前提に製作したので、スケール感はイマイチです。
何回も飛行させました。20~30フライトはしたと思います。


A-380の飛行
A-380の製作記事はこちらです。