DJI製 NAZA(マルチコプター用コントローラ)を購入しました。

マニュアルや設定のためのアプリケーション(アシスタント ソフトウェア)は、DJIのサイトがらダウンロードします。
まず、(英語の勉強も兼ねて)、日本語マニュアルを作成しました。
日本の販売店では、「日本語マニュアル」付とかで、販売されているお店もあるようですが、どのようなものか見ていません。
私は、できるだけ原文に近いように、図も入れて、原文と同じ40ページのマニュアルを作成しました。
◆ DJI NAZA取扱説明書(日本語マニュアル)
これは、原本「Naza User Manual v2.4」を元に、日本語版として私が作成したものです。
信頼性はまったくありません。
![]() DJI NAZA取扱説明書(日本語マニュアル)のダウンロード
DJI NAZA取扱説明書(日本語マニュアル)のダウンロード
空撮用のマルチコプターに搭載予定です。
フレームは、STO S-606で、X6タイプ(DJIでは、Hexa-rotor Vと呼んでいます)です。
受信機は、JRのRD931を予定していますが、 スイッチなどの割り当ての都合でHITEC OPTIMA9に換えるかもしれません。 HITECのAURORA9は、チャンネルやスイッチ、スティックの割り当てが、自由にできます。
ハードウェアの接続です。 (日本語訳が、間違っていたらごめんなさい)
画像をクリックすると拡大されます。
コントローラー本体は
MCと呼ばれて、この中に、加速度センサー、気圧センサー、ESCの制御を内臓しています。
GPS/コンパスは
GPSによる位置情報と、磁気コンパスによる方位情報を取得します。
V-SENは
VUと呼ばれていて、スイッチングBECとNAZAの状態を表示するためのLED、アシスタントソフトウェアと通信するためのUSBインターフェイスを内蔵しています。
BEC出力は5Vで、電流容量は不明です。
ここで、気が付いたのは、コントローラー本体において
各ポート(左右共)の電源(+)とGND(-)は、すべて内部で接続されています。

つまり、どこのポート(端子)からでも、電源が供給できるわけです。
BEC付ESCを接続すればMCは働きます。 しかし、MCには電圧モニター機能があり、エラーメッセージがでます。
したがって、動力用バッテリーを使って、VU内臓のBEC経由でMCに電源を供給しないといけないみたいです。
そうした場合、VU内臓のBEC出力と全てのESCのBEC出力が並列接続されます。
電位差が生じた場合、循環電流が流れます。
以前のTMFでも、ESC接続端子において、電源とGNDは、すべて内部接続されていました。
同じ製品において、ESC内臓のリニアBEC(レギュレータIC)の個体差が、0.1V位ありました。
また、温度-電圧特性が、負のものと正のものとがありました。
結果、
6個並列にしたからといって、必ずしも電流容量が6倍にはなりません。 出力電圧の高いものに負担がかかります。 しかも、そのBECの温度-電圧特性が正ならば、さらに激しく差が開きます。
現実、6個のうち、1個だけ発熱量が大きかったです。
というわけで、
今回は、スイッチングBECとリニアBECとの並列接続になるわけです。
コントローラーが0.3A と小型サーボが4個付きますので、
電流容量的には、VU内臓のBECのみでOKのような気がしますので、
1) ESCの(+)線を全て抜いて、使ってみます。
それで、電圧降下やサーボを動かしたときの電圧変動が大きかったら、
2) 相性の良いESCのみ(+)線を接続する。
といった方法で、試してみるつもりです。
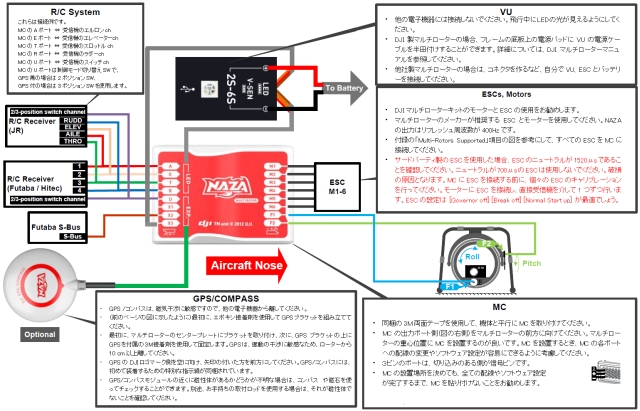
コメント (1)
はじめまして。
まったくの初心者が自作ドローンを落札してしまいました。
ご想像通りの状態になっています。
ぜひ参考にさせていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
投稿者: うっかりいちべえ | 2017年08月21日 11:37
日時: 2017年08月21日 11:37